
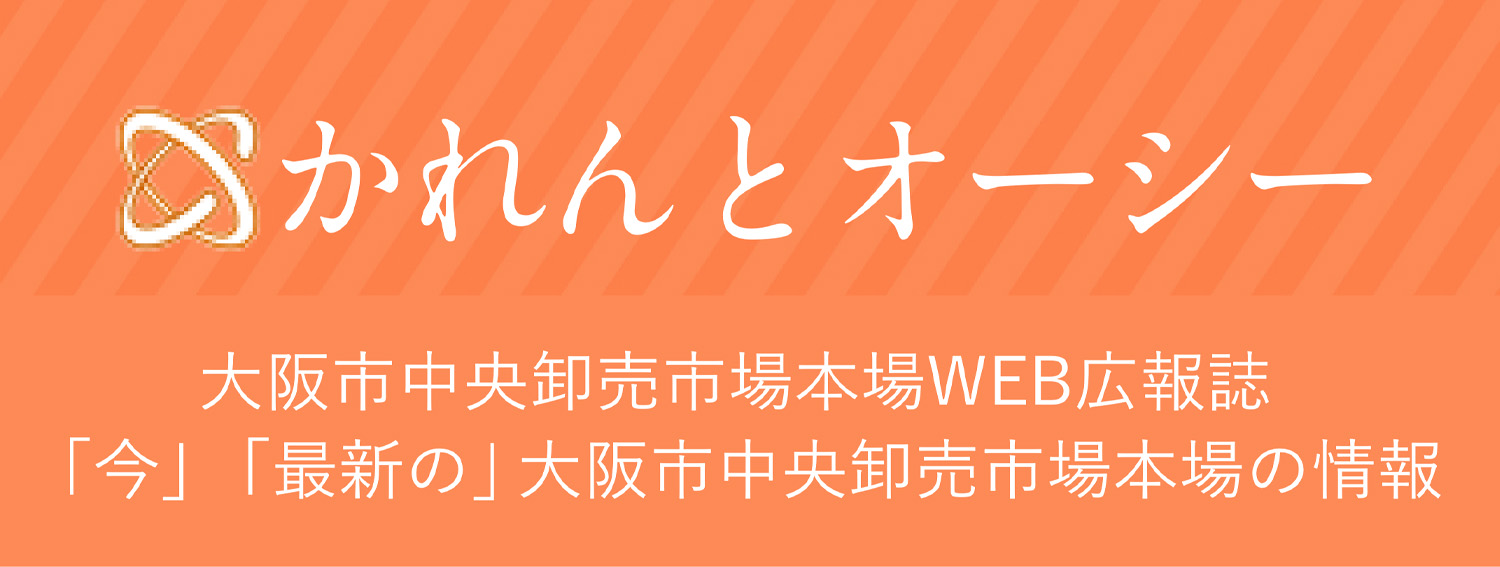
大阪市中央卸売市場食品衛生検査所

寄生虫による食中毒のうち発生件数が多いのはアニサキスで、vol.116(https://honjo-osaka.or.jp/currentoc/vol-116/)でも取り上げましたが、他にも寄生虫による食中毒があることをご存知でしょうか。
その一つが Kudoa septempunctata(クドア・セプテンプンクタータ) による食中毒で、毎年 20 件前後、患者数にして 200人前後の食中毒が発生しており、見逃せない食中毒の一つです。
そこで今回は「クドア」についてのお話です。食品を適切に取り扱うことで食中毒のリスクを抑えることができるので、正しい予防方法を知って、楽しい食生活を送りましょう。

クドア・セプテンプンクタータは、ヒラメに寄 生することが知られており、クドア・セプテンプンクタータが寄生したヒラメを生又は加熱や冷凍が不十分な状態で食べると、約 2 時間~20 時間で下痢・嘔吐を引き起こします。
症状は軽く、多くの場合、発症後 24 時間以内 に回復し、後遺症もないと言われています。
クドア・セプテンプンクタータは、冷凍や加熱で死滅します。
ただし、その温度と時間には注意が必要です。冷凍なら-20°Cで4時間以上、加熱なら中心温度 75°Cで5分間以上です。
凍結した後に食べる、もしくは加熱して食べることで食中毒を防止することができます。
ヒラメの養殖地では、クドア保有稚魚の排除や、出荷前にクドア・セプテンプンクタータの寄生がないことを検査で確認する等の取組が行われています。
事業者は、生食用のヒラメを提供する際には、クドア陰性と確認されたものを使用しましょう。

最近では、ヒラメ以外の魚を生で食べることでクドア様食中毒症状をきたす事例が報告されており、クドア・セプテンプンクタータ以外のクドアによる寄生が原因と推定されています。

食品衛生検査所では、2024 年 3 月から 1 年間をかけて、大阪市中央卸売市場本場に流通する鮮魚(マグロやサワラ、カンパチ、マアジ、アカガレイ 等を含む全 373 検体)を対象にクドアの寄生実態を調査しました。
その結果、ヒラメ以外の魚類でもクドアの寄生があることが分かりました。
食品衛生法では、ヒラメの筋肉1g あたりのクドア・セプテンプンクタータの数が 100 万個を超えるものは販売が禁止されています。
それを超える数が検出されたのは一部でしたが、クロマグロの幼魚であるヨコワ、サワラ(サゴシを含む)及びアカガレイでは特に高確率でクドアが検出され、クドア・セプテンプンクタータとは異なる種類のクドアが寄生していました。
これらのクドアが、ヒトに対して病原性を持つかどうかは今のところ不明であり、今後の研究成果が待たれます。
不用意に恐れる必要はありませんが、リスクが潜んでいることを理解し、「新鮮だから」という個人の判断で、「刺身」や「タタキ」対象魚種を開拓することは注意が必要と言えるでしょう。

食欲の秋となり、秋の旬の味覚が楽しみとなる季節がやってきました。9月から 11 月は、キノコ狩りをする方も多いでしょうか。
実は、毒キノコには、食用キノコとそっくりのキノコがあります。触れるだけでも炎症を起こし、食べると死亡するキノコもあります。
毒キノコを食用キノコと間違えて食べたり、有毒植物を食べたりして食中毒になる事例が毎年のように発生しています。

右図のように、毒キノコによる食中毒の発生は 9 月から 11 月にかけて顕著に増加します。4 月から 7 月にかけて毒キノコ以外による植物性食中毒が増えているのは、山菜採りが活発な時期となり、有毒植物の誤食が原因です。
食用と確実に判断できないキノコや山菜等は採らない、食べない、売らない、人にあげないでください!!食べた時強い苦みや舌のしびれを感じたら、食べずにすぐに吐き出してください。もし間違えて食べてしまって体調不良を感じたら、医療機関を受診するようにしましょう。
観賞植物の中には有毒なものがあります。食用と間違えて食べないようにしましょう。
家庭菜園を行っていると、次第にエリアを広げたくなり、ついつい狭いスペースも有効活用して栽培エリアを作りたくなってしまうことも多いですよね。

しかし、安全に家庭菜園を楽しむために、
食用と園芸の種類が混じらないように 区画する。
何を植えたのかを分かるようにする。
ことを守りましょう。
厚生労働省のホームページでは、毒キノコや有毒植物に関する情報がまとめられていますので、是非参考にしてみてください。
2025年7月3日、10日
弊社うおいちでは、中央卸売市場の水産荷受会社の責務として、「水産物をコアとし、お客様に価値ある商品とサービスを提供することにより、食文化の発展に貢献します。」という経営理念のもと、魚食文化に触れる機会を提供することで、これからの水産業・卸売業について考えていただくことを目的に食育活動を継続しております。
今回のお料理教室では、摂南大学様にて 7月3日、10日の2日間に渡り 農学部食品栄養学科の2年生(計77名)を対象に行いました。共催は鳥取県関西本部様、JA全農とっとり様、協賛はJF全漁連様になります。
今回のレシピは、
という、鳥取県の食材をふんだんに活かしたものとなりました。
初めて魚を捌く学生も多いとのことでしたので、アジの特徴を話しながら、工程ごとに丁寧な説明を心掛けました。学生さん達もかなり意欲的に取り組んでおり、わからないところも友達同士で教え合いながら、挑戦しているようでした。アジはお刺身、ムニエルにていただきましたが、魚1匹を捌いて調理するところまで自分の手で行ったことにより、達成感が大きかったと思います。
湖山池産のヤマトシジミも、通常よりはるかに大きい規格で選別されたものを使用しました。中には40㎜に近いシジミも混ざっており、驚きの声があがっておりました。殆ど調味料を入れなくても、うまみが強く出たシジミ汁に仕上がり、美味しく頂きました。その他にも、すりおろしても持ち上げられるほど粘り気が非常に強い「ねばりっこ」の山かけごはん、甘みのある焼き白ネギ、デザートのスイカ等、鳥取県の特色が強く出た食材を楽しむことができました。
アンケートにて、学生からも、「魚を捌く楽しさを知りました」「普段食べているお寿司やお刺身に今回体験した工程があると思うと、想像以上に大変だと思った」「家でもやる機会があればしてみたいなと思った」といった声がたくさんありました。将来、栄養士や管理栄養士など食に関わる仕事につくかもしれない学生たちにとって、今回の実習で学んだ事を活用して水産や魚食に興味を持つきっかけ、そして水産業界に関わる行動源となればいいと思っております。
最後になりましたが、この様な機会をくださった摂南大学の先生方、共催の鳥取県関西本部様及びJA全農とっとり様、協賛のJF全漁連様に感謝申し上げます。
今後も弊社は、様々な形で産官学(生産者・行政・学校・販売)と連携しながら持続可能な食育活動を推進していきます。










各支社で「のぼり」を立てて、さかなの日をアピールしています!








大阪市水産物卸協同組合
大阪市水産物卸協同組合(髙丸 豊理事長)では、令和7年8月5日に福島区役所2階において開催されました「令和7年度 福島区食育展 食育なつまつり」の食育展示コーナーに出展しました。大阪おさかな普及協議会主催のおさかな絵画コンクールの入選作品を展示した他、入選作品をデザインに取り入れたクリアファイルを提供し、来場者にお持ち帰りいただきました。
「いろんな魚にさわってみよう!お魚タッチ!」と題し、アジ、ハモ、トビウオ、センネンダイ、アマダイ、イワシの展示を行いました。来場した子どもたちは、丸の魚を目にすることが初めての皆さんが多かったようでしたが、ほとんどの子どもが実際に魚にさわったりつかんだりして魚とのふれあいを楽しんでいたようでした。


作品募集中 ! !
作品出品、よろしくお願いします。
| 展示作品 | 写真・絵画・書道・手芸・生花 他 |
| 応募資格 | 本場市場協会会員団体に所属し、当市場に常時勤務する者(組合員、従業員《OB含む》の家族・親族含む) |
| 受付締切日 | 9月22日(月) |
| 受付場所 | 各所属で取りまとめて、業務管理棟 2階 市場協会までお持ちください。 |

| 日時 | 10月23日(木)~ 10月25日(土) 23日(木)24日(金)午前9時~午後4時 25日(土)午前9時~午後1時 |
| 展示場所 | 大ホール(業務管理棟16階) |
場内で働く皆さんの力作ぞろい ぜひご覧ください
資料室は下記のとおり業務しております
・土曜日以外の開場日
・午前9時~午後3時
静かな環境で、ゆっくり、各種の資料をお調べいただけます。
閲覧用の新聞は次のとおりです
・日本経済新聞・日経MJ・みなと新聞
・水産経済新聞・日本食糧新聞・農経新聞・食品市場新聞
| 木村彰利 著 『流通環境の変化と青果物仲卸業者』 | (筑波書房) |
| 大西睦子 著 『徳家秘伝 鯨料理の本』 | (講談社) |
| 『野菜情報』 7月:信州大学発「信大BS8-9」夏秋いちごの常識を覆し、全国に栽培拡大! 8月:気候変動待ったなし!野菜の生産・流通現場の適応策 9月:農園のある病院 リハビリとして農作業に取り組む | (農畜産業振興機構) |
| 『果実日本』 7月:労働力確保の取組み 8月:カキ産業を展望する 9月:カンキツ栽培の最新動向 | (日本園芸農業協同組合連合会) |
|
『全水卸2025』 7月:「物流機能中心の市場施設」とは何か 9月:ベーシック経済学と水産マーケットはタダでは沈まない | (全国水産卸協会) |
| 『アクアネット』 6月:養殖魚の重要疾病と対策 2025 Part 2 7月:魚を美味しく焼く ~温故知新と新潮流~ 8月:漁業・養殖業における食害対策 ~生産物を守る技術開発最前線~ | (湊文社) |
| 『海外漁業協力』 №111:世界の魚市場 ペルー共和国 カヤオの魚市場 | (海外漁業協力財団) |
| 『日本水産資源保護協会季報』 №582:2025春 | (公益社団法人日本水産資源保護協会) |
| 『FRANEWS』 Vol.83:食害 ~水産物を守る工夫~ | (国立研究開発法人水産研究・教育機構) |
| 『食と健康』 7月:食品取扱い施設のネズミ・昆虫対策 8月:夏場に注意したい! 食中毒対策 | (日本食品衛生協会) |